HOME» ■ CREATIVE #04 »ユーザー目線のデザイン vol.3
■ CREATIVE #04
ユーザー目線のデザイン vol.3
古びるデザイン・古びないデザイン
 河田氏:結局それは、クライアントのためのデザインになっているのか、ユーザーのためのデザインなのかというところを、やっぱりデザイナーは考えないといけないと思うんです。
河田氏:結局それは、クライアントのためのデザインになっているのか、ユーザーのためのデザインなのかというところを、やっぱりデザイナーは考えないといけないと思うんです。やはりクライアントの気持ちに沿って、ユーザーの気持ちになって、新しいデザイン、長く使えるデザインを作っていきたいと思います。
南氏:それにはやはりちゃんとした生活?
河田氏:それと本物を知ること。世で本物と言われるものと付き合ってみたいと思いますね。本物とニセモノを見分ける近道って本物だけつきあうことと言われているように。
昔にデザインされて今も現役で売れているものって、絶対なにかあると思う。逆に同じようにデザインされてるものでも、賞を取ったりしているものでも、そのときキレイだなと思ったものでも、何年後かには、なんか古くなったように感じるものがあるんですよ。
その違いが何なのかってのを使いながらじっと考えたりします。なんで古びるデザインと古びないデザインがあるのか。やっぱりデザイナーですから、古びないデザイン作りたいじゃないですか。
有名で売れてるってのもあるんだろうけれど、じゃあアルネ・ヤコブセンの椅子が有名だからってだけで売れているかといえば、そうじゃないものがあるはず。で、買って使ってみる(笑)
南氏:うんうん。使うと違いますよね。
河田氏:やっぱり飽きないんですよ。あるだけで、佇まいが違う。それって何なんだろうなとずーっと考える。普通の人はいいなと思うだけなんだろうけど。
 南氏:ナガオカケンメイさんのお店って、古くても良いもので、自分の感性に合ったものを見つけてきて、見せ方を変えたり、カタログを変えるなどの売り方を変える、いわゆるリノベーションするスタイル。
南氏:ナガオカケンメイさんのお店って、古くても良いもので、自分の感性に合ったものを見つけてきて、見せ方を変えたり、カタログを変えるなどの売り方を変える、いわゆるリノベーションするスタイル。ここのお店に行くと、無名でも何十年も前に作られたデザインのものでも、こう、見て心躍るようなものがあるんです。
大野氏:いまここにあってもぜんぜんおかしくないでしょ?
南氏:そう。それって何かというと、一つに素材だと思うんですね。今めちゃくちゃ最先端の素材で、打ち上げ花火みたいに尖ったものを作っても、そのときの時代性に合いすぎて、何年かすると古く感じてしまうものってある。
大野氏:古びていく良さもあるんですけど、時代を感じて、もうこれ使いたくないなと思っちゃう古さもありますよね。
河田氏:一番良いのは、古くなったほうが良くなるもの。
南氏:経年変化。。ですね。
大野氏:今回私たちが作ってる「裁縫箱」は、長く使ってもらって古びていく良さを味わってもらえるかなと思って作ったんです。
 河田氏:今の子供たちは、チャックがついてる裁縫バックなんです。それはそれで、ある意味使い易いのかもしれないし、やっぱり安価だったりする。
河田氏:今の子供たちは、チャックがついてる裁縫バックなんです。それはそれで、ある意味使い易いのかもしれないし、やっぱり安価だったりする。でもそこにちょっと(時代を)戻すようなんですけど、木でできてる箱で、使えば使うほど味わい深くなるものを提案したんです。
派手でファンシーな裁縫バックって、子供はその時ぱっと飛びつくかもしれないけど、こっちのほうがずっと飽きずに使うことができる。
ものの寿命を延ばすのもデザインの仕事だと思うんです。ずっと使える、大事に使えるというものをデザインするっていう。
南氏:余白がないといけないのかなとも思いますね。ヘンにデザインを与えすぎるよりも、シンプルにしてて、そこに思い出だとか自分の傷が入るという場所というか。
河田氏:自分でカスタマイズできる・・。それに、ずっと使えるものとそうでないものを選ぶ目ということも大事かなと。カッコ良いデザインと売れるデザインって違ってて、愛されて長く使えるデザインが売れるデザインだと思うんですね。みんなの生活の中に溶け込むような感じ。
南氏:デザインだけでなくて、いろんな業界で長く残っている企業や建築や人も、そこにある理由を探るのもひとつの刺激ですね。
大野氏:シンプルな良いカタチって、長く残ってくるんですけど、私たちが考えるシンプルなものって、実は昔の人も思いついててて既にあったりします。
「あ、やっぱり、これってみんな思いつくものなんだ」となるんですが、それを知らないで、クライアントに提案してしまったとしたら、それはたとえ自分のデザインでも、「二番煎じ」にしかならない。だからこそ昔の人や、他の人の作品を見ることって、すごく大事なことですね。
 河田氏:シンプルなものでも古びるものは古びる、結果って年月たたないとわからないんですね。それを作るのが一流なのかなと。。
河田氏:シンプルなものでも古びるものは古びる、結果って年月たたないとわからないんですね。それを作るのが一流なのかなと。。でも、結局、デザインが良いか悪いかって、私は、個人の主観でしかないと思うんですよ。シンプルで長く使えるものが絶対みんなが好きかというと、そうじゃないですしね。
そういう意味で、他者を知るということも必要だと思うんですよ。どうしてもいつのまにか視野って狭くなるから、いろいろ他人を知った上で自分を知るという感じかな。
南氏:最終的にはデザイナーの人間性ともなりますかね。やはり見たり聞いたり、やってみたりの経験からしか出てこない。
河田氏:そうやって自分の実体験の中で取り入れたものを、クライアントにうまくプレゼンできて、理解してもらうことってデザイナーにとって必要だと思う。
南氏:デザイン以外の説得力って必要になってきますね。その中でも自分の美意識の中で、クライアントの意見とぶつかる点もあると思うんですけど。
河田氏:私たちデザイナーが勝手に作るというのではなく、その商品をデザインの力で優れたものにしたいという考えに沿って、やはり地に足がついたデザインであって、実際に(商品の)売上に繋がっていくものを作らなければと思います。
大野氏:「デザイナー自身が理想とするデザイン」とビジネスとはやっぱり別で、そのバランスですね。両方必要ですし。
南氏:そうですね。理想とするデザインの比率を大きくはしたいですけどね。

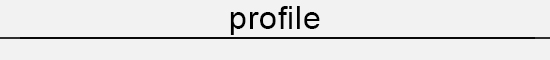

南 大成
プロダクトデザイナー
HIROMINAMI.DESIGN
鹿児島県生まれ。2006年、英国シェフィールドハーラム大学、BAプロダクトデザイン学部を卒業。デザイン事務所勤務、グラフィックプロダクション勤務を経て2011年に独立。アイデア先行型デザインが市場に溢れる中、自身が一生活者として実生活で使えるデザイン「生活者視点のデザイン」を理想として掲げ活動中プロダクトデザイナー
HIROMINAMI.DESIGN
HIROMINAMI.DESIGN
HP: http://hirominami-design.com/index.html

大野 典子
グラフィックデザイナー
1972年栃木県生まれ。2006年女性3人のデザインユニット、ansy graphics(アンジーグラフィックス)設立。グラフィック、パッケージ、テキスタイルデザインを担当。消費者の視点に立ったデザイン、生活にうるおいを感じることができ、無駄のない豊かさのあるデザインにこだわりを持ちたい。グラフィックデザイナー
合資会社アンジーグラフィックス
HP: http://www.ansy-g.com/

河田 朗子
グラフィックデザイナー
大阪府生まれ。一般企業に就職後、結婚を機にグラフィックデザイナーを志し、2006年のansy graphics設立に携わる。グラフィック、イラスト、テキスタイルを担当。人の気持ちに寄添うスタンスを大切にしている。人と環境に優しく、心豊かな暮らしにつながるデザインを考えてゆきたい。グラフィックデザイナー
合資会社アンジーグラフィックス
HP: http://www.ansy-g.com/
撮影:菅野 勝男/取材:2012年5月
2012/05/10
